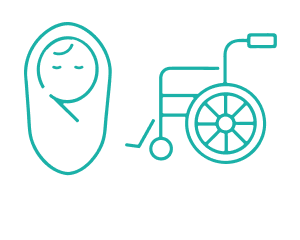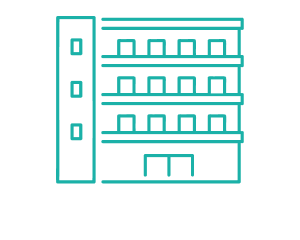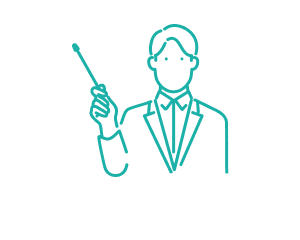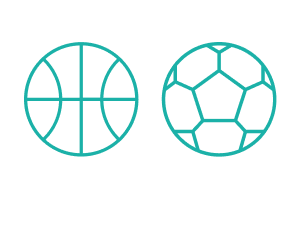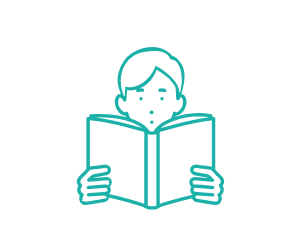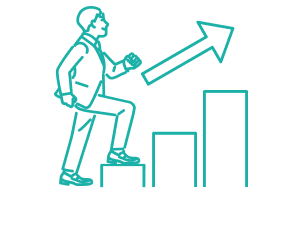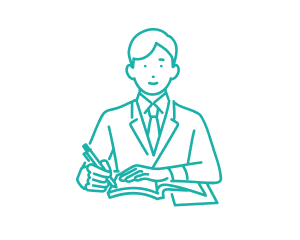福利厚生・サポート制度
Welfare and Support
社員一人ひとりが安心して働ける環境づくりは、企業の成長・拡大のための土台となります。
十全化学では、この理念を基に、社員がそれぞれの個性を活かし、安心して業務に取り組めるよう、ワークライフバランスを重視した休暇制度、キャリア支援の研修、健康面でのサポートなど、さまざまな制度やサポートを多角的な取組みを行っています。
- 01 福利厚生
- 02 教育研修制度
- 03 働き方・ダイバーシティ
- 04 社内交流
福利厚生
Job Description休日や休暇、働き方に関する制度
-

休業制度
育児休業制度・介護休業制度があります。
-

短時間勤務制度
育児短時間勤務・介護短時間勤務制度があります。
-

産前産後休暇
育児休業産前・産後休暇がおよび育児休業制度があります。
-

再雇用制度
定年退職後の再雇用制度があります。
-

社宅制度
住宅費支援で新生活を快適にサポートしています。
-

食事無料
健康的な無料食事で日々の生活を充実。
-

メンター制度
経験豊富な先輩による手厚い成長支援が受けられます。
-

プロスポーツ
観戦チケット人気プロスポーツのエキサイティングな試合観戦を無料で楽しめます。
教育研修制度
Training and Development表彰・学習に関する制度
-

優秀従業員表彰
顕著な成果を上げた社員を特別表彰しています。
-

改善提案表彰
革新的な提案を行った社員を評価しています。
-

永年勤続表彰
長年の貢献に対し感謝の意を表し表彰いたします。
-

各種研修制度
スキルアップを目指す多彩な研修プログラム。
-

自己啓発支援
自己成長のための学習支援を実施。
-

各種資格取得支援
資格取得に向けた費用支援や勉強会提供。
働き方・ダイバーシティ
Working Style and Diversity十全化学では、すべての社員がその能力を十分に発揮し、働きやすい職場環境を整えるため、ダイバーシティの一環として、育児や介護をする社員へのフォロー体制、「女性活躍推進法」に基づいた行動計画の実施しています。
育児休暇取得
生まれた我が子の可愛さと、
会社の有難みに浸る貴重な時間に。
A.Y営業部 営業課
2016年 入社
「育児休暇取得」取得しようと思ったきっかけを教えてください
もともと妻の出産後はしばらく里帰りする計画までは立てていたのですが、その後の3人での暮らしについても不明な点や不安な面が多ったため、里帰り後の育児休業の取得を検討し始めました。
新しい生活サイクルが落ち着くまでの期間を想定し、夫婦での子育てプランを組み立て、収入面や職場復帰の負担も考慮した上で、「無理のない形で活用してみよう」という話となり、1か月間の取得を決めました。

取得する際に抵抗や不安はありましたか?
私の所属する部署は少人数で、お客様にも個人で関わることが多く、常に密なやり取りをしながら業務を進めています。
そのため、1か月間の育児休業でも、先方に迷惑をかけたり、上司や同僚の業務負担も大きくしてしまうのではないかという懸念もあり、相談自体への抵抗は少なからずありました。
また、私が育児休業を取得する以前は男性社員の取得実績が乏しく、社内での反応も予測できなかったため、不安もありました。
取得してみて、周りの反応はどうでしたか?
想像以上にすんなりと、あっけなく受け入れていただき、私の不安は杞憂に終わりました。
上司に相談すれば「もっと休めばいいのに」と言っていただき、自ら私の業務の全てを引き継いでいただけたため、同僚への業務負担増加もなく、安心感と歓迎ムードが広がりました。
妻のほっとした表情が印象的で、そこにも安心できましたね。
また、取引先は概ね大手企業のため、「育休」への理解が深く、業務の引継ぎも終始スムーズでした。
「育児休暇取得」を取得した効果や良かった点を教えてください
赤ちゃんの手のかかり方はそれぞれだと思いますが、我が子の場合は寝かしつけの大変さが想像を超えていたので、改めて夫婦で子育てに集中できる期間が得られて良かったなと思っています。
また、赤ちゃんの成長はとても早く、日々変化するその姿を見続けられた時間は、プライスレスなものとなりました。
そして、休暇を挟むことで職場のありがたみも実感でき「復帰後は仕事ももっと頑張ろう!」という思いが強まりました。

短時間勤務
恐縮ではなく感謝を伝え、
新制度活用のロールモデルに!
H.M品質管理部 試験課
2006年 入社
「短時間勤務」取得しようと思ったきっかけを教えてください
第3子の育休明けと上の子の小学校入学のタイミングが重なったのですが、保育園に預ける第3子より、むしろ新しい環境に馴染んだり、宿題を見たりする必要のある小学生のケアを重視しようと考え、時短勤務を選択しました。
ある程度の生活を送るためには収入の安定も大事ですが、無理をすれば結果的に退職となるかもしれません。
制度の改正で小学校4年生までが対象となった時短制度を、長く働くために選びました。

取得する際に抵抗や不安はありましたか?
新しい制度を利用しての時短勤務社員としては第一期となりますが、今回はキャリアを積んでからの出産ということもあり、抵抗や不安はありませんでした。
もともと後輩のためのモデルケースになりたいと考え、積極的に制度を利用する考えでしたので、上司には妊娠を報告する流れで、復帰後の時短勤務への変更も申し出ました。
先輩がサクッと制度を利用する姿を見て、誰もが引け目を感じない風潮が広まっていけば嬉しいですね。
取得してみて、周りの反応はどうでしたか?
ネガティブな反応はなく、むしろ時間を過ぎると「帰らなくて大丈夫?」と声をかけられますし、勤務時間に収まるよう業務を組ませていただいています。
私はそんな気遣いに対し、「申し訳ない」ではなく「ありがとう」を伝えることにしています。
後輩にも「できるようになってから返せばいいんだよ」と呼びかけ、制度の説明も行ってきたからか、今では産休から時短勤務での復帰を目指す若手も増えてきました。
「短時間勤務」を取得した効果や良かった点を教えてください
帰宅後は小学生の宿題を見たり、習い事の送迎や連絡帳を確認しての翌日の準備、第3子のご飯やお風呂、寝かしつけと分刻みの生活のため、会社にいる方が落ち着き、出社後にいただくコーヒーが癒しになっています。
また、自分の時間配分で行える仕事の内容に以前よりもありがたみを感じ、「量より質」を意識するようにもなりました。
部員の7割が女性の部署ですので、みんなで協力できる体制をより一層、整えたいと考えています。

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
1. 計画期間
2025年1月1日 ~ 2026年12月31日
2. 目標と取組内容・実施時期
目標1
「元気とやま!子育て応援企業」へ登録し、全社員が仕事と各ライフイベントを両立しながら意欲的に働ける環境を進化させていく。
実施時期・取組内容
- 2025年1月~
- 「元気とやま!子育て応援企業」へ登録申請の登録を行う。
- 2025年1月~
- 2025年10月の法改正に向けた制度設計を検討していく。
- 2025年2月~
- 登録終了後、社員への登録の経緯と内容を広報し、男性社員もより育児への参画意識を高める。
- 2025年3月~
- 法改正を含めた内容で、管理職はじめ全社員へ制度理解のための研修を実施する。
- 2025年9月~
- 両立支援アンケートを実施し、効果測定を実施し、終了後に社員へ結果の共有をする。また、アンケートの分析を行い、改善点を抽出する。
- 2025年10月~
- 「ファミリーデー」を開催。お子様に両親が働く会社に興味をもってもらうことで、親子のコミュニケーションの機会創出を狙う。
- 2025年12月
- 業績報告会にて、1事業年度の男女育児休業利用者を報告し、制度利用実績の共有を行う。
- 2026年2月~
- 育児介護休業関連の制度利用実績及び、課題分析を行い、女性活躍推進データベースへ情報の更新を行う。
- 2026年9月~
- 両立支援アンケートを実施し、効果測定を実施。終了後に社員へ結果の共有をする。また、アンケートの分析を行い、改善点を抽出する。
- 2026年10月~
- 「ファミリーデー」を開催。お子様に両親が働く会社に興味をもってもらうことで、親子のコミュニケーションの機会創出を狙う。
- 2025年12月
- 業績報告会にて、1事業年度の男女育児休業利用者を報告し、制度利用実績の共有を行う。
目標2
男女とも育児休業の取得率80%以上とするため、育児休業を取得予定の社員及び育児休業から復職した社員に対する、制度推進役やメンターとしての役割を担う、両立支援サポーターを新設する。
実施時期・取組内容
- 2025年1月~
- 2024年度の育児休業取得率を集計し、社内外へ広報する。その際、取得促進を促すため、育児休業制度及び両立支援制度についてもあわせて広報する。
- 2025年1月~
- 一般事業主行動計画をサポーターへ共有。取り組みの方向性を一致させる。両立支援サポーターと直接相談できる「サポーター相談窓口」を開設し、社員へ共有する。
- 2025年2月~
- 両立支援イベント(座談会・情報交換会・勉強会等)の年間計画をたて、全社員に広報する。
- 2025年2月
- 2025年4月に実施される法改正の内容をサポーターへ共有し、知識を最新の状態へ更新するとともにハンドサイトの改訂を行う。
- 2025年4月
- 新入社員(新卒・中途)、及び参加希望者へ両立支援制度についての説明会を実施する。
- 2025年8月
- 2025年10月実施される法改正の内容をサポーターへ共有し、知識を最新の状態へ更新するとともにハンドサイトの改訂を行う。
- 2025年9月~
- 管理職者へ両立支援制度についての研修を実施し、知識の再構築を行う。研修後、管理者によるイクボス宣言(厚生労働省イクメンプロジェクト、及び富山県イクボス企業同盟とやま)ができるか検討する。
- 2025年11月~
- 両立支援サポーター増員のための説明会、及び活動内容の報告会を実施する。
- 2026年1月~
- 2025年度の育児休業取得率を集計し、社内外へ広報する。その際、取得促進を促すため、育児休業制度及び両立支援制度についてもあわせて広報する。
- 2026年2月
- 両立支援イベント(座談会・情報交換会・勉強会等)の年間計画をたて、全社員に広報する。
- 2026年4月
- 新入社員(新卒・中途)、及び参加希望者へ両立支援制度についての説明会を実施する。
- 2026年11月~
- 両立支援サポーター増員のための説明会、及び活動内容の報告会を実施する。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
1. 計画期間
2025年1月1日 ~ 2028年12月31日
2. 目標と取組内容・実施時期
目標1
管理職に占める女性労働者の割合を10%以上へアップさせる。
実施時期・取組内容
- 2025年1月
- 各人の年間目標、前期目標のすり合わせを上長と行い、キャリアビジョン及び目標達成に向けての効果測定を1ヵ月に1度1on1を継続的に実施していく。
- 2025年7月
- 半期の振り返りを行い、後期目標のすり合わせを上長と行い、目標達成に向けての効果測定を1ヵ月に1度1on1を継続的に実施していく。
- 2025年8月~
- 次期管理職者へのキャリアアップ支援として、チーフ・リーダー研修を実施し、マネジメント意識の向上をはかる。
- 2026年1月
- 各人の年間目標、前期目標のすり合わせを上長と行い、キャリアビジョン及び目標達成に向けての効果測定を1ヵ月に1度1on1を継続的に実施していく。
- 2026年7月
- 半期の振り返りを行い、後期目標のすり合わせを上長と行い、目標達成に向けての効果測定を1ヵ月に1度1on1を継続的に実施していく。
- 2026年8月~
- 次期管理職者へキャリアアップ支援として、チーフ・リーダー研修を実施し、マネジメント意識の向上をはかる。
- 2027年1月
- 各人の年間目標、前期目標のすり合わせを上長と行い、キャリアビジョン及び目標達成に向けての効果測定を1ヵ月に1度1on1を継続的に実施していく。
- 2027年1月~
- 行動計画前半を終えての結果及び、産業別平均値との差異を確認し、振り返りと目標に対しての効果測定を行う。
- 2027年7月
- 半期の振り返りを行い、後期目標のすり合わせを上長と行い、目標達成に向けての効果測定を1ヵ月に1度1on1を継続的に実施していく。
- 2027年8月~
- 次期管理職者へのキャリアアップ支援として、チーフ・リーダー研修を実施し、マネジメント意識の向上をはかる。
目標2
年次有給休暇の取得率を全部門60%以上にする。
実施時期・取組内容
- 2025年1月~
- 本行動計画を周知し、有給休暇取得日数増加の啓蒙活動を実施する。誕生日や記念日等に有給休暇取得を推奨する。
- 2025年4月
- 2025年3月までの1年間の取得状況を調査し、部署別の有給休暇取得傾向を把握する。
- 2025年4月~
- 業務改善による業務の効率化を図り、計画的な業務遂行を促進することで休暇が取得しやすい環境の構築を図る。
- 2025年7月~
- 調査した部署別の有給休暇取得状況より、取得率が低い部署の抱える問題点を該当部署と総務部とで協議し、解決策を検討、実施する。
- 2026年1月~
- 本行動計画を再周知し、有給休暇取得日数増加の啓蒙活動を実施。 誕生日や記念日等に有給休暇取得を推奨する。
- 2026年4月
- 2026年3月までの1年間の取得状況を調査し、1年の活動結果を総括したうえで2026年度の取り組み内容を策定し実践する。以降活動を継続する。
- 2026年4月~
- 1年間の取得状況の視点から業務効率化活動の効果を検証し、更なる業務効率化活動を推進する。以降活動を継続する。
社内交流
meetup長く働き続けてもらうための会社づくりには、良好な人間関係の構築も必要だと考えています。
良好な人間関係により、社内コミュニケーションがスムーズになり、業務効率の向上や、組織が活性化されると考えています。
そのため、十全化学ではさまざまな形で、社内コミュニケーションを行っています。


当社では、夏と冬に社員同士の交流を深めるために懇親会を開催しています。
夏の懇親会では、ゲーム大会など様々な企画を行い、楽しく交流する機会を設けています。
一方、冬の懇親会では、その年のMVP社員や改善提案を行った方々を表彰する場を設け、その功績を称えながら、温かい雰囲気の中で親睦を深めます。
これらの懇親会は、普段の業務では見ることのできないメンバーの別の一面を垣間見ることができ、社員同士の親交が深まる素敵な時間となっています。
部活動紹介
野球部、ゴルフ部、テニス部、ランニングクラブ、ワンダーホーゲル部(山登り)、釣り同友会